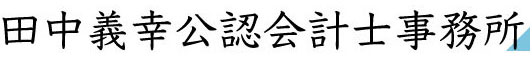コラム
手帳の切れ端
2025年2月20日
お昼ご飯を御馳走になっているときに、無造作に「田中さんはどうして公認会計士になったんですか?」と聞かれた。とっさに、「昼飯ぐらいで、そんな大事なこと教えられませんよ」とでも言えればよかったのだが、言葉が出てこなかったので、そのときはそっけなく、「もう忘れました」と答えた。「なにしろ、四十年も前のことですからね」と少し悪びれた風の弁解をしながら。でも、どうしてだったかなという思いは自分の中にも残った。
僕は、そのとき三十歳になったばかりだった。それまで生きてきた世界と訣別して、全く縁のなかった実学の世界に行こうと思ったとき、公認会計士という職業があることを初めて具体的に知った。最初の試験に落ちたとき、自分の悪筆が原因だと思って、けなげにもそれから一か月間朝から晩まで字の練習ばかりした。また、試験科目の経済学の勉強が面白くなり、なんとかこのまま経済学者になる道はないかと詮無いことを夢想したが、あるはずもなく、三十一歳でこの仕事に就いた。
このあいだの日曜日の日本経済新聞の第一面に詩人の茨木のり子の記事が載っていて、「自分の感受性ぐらい 自分で守れ ばかものよ」という詩の一節が抜粋されていた。
そういえば、前にある人からこの詩を書いた手帳の切れ端をもらったことがあったのを思い出し、引き出しの奥にしまってあったのを探し出した。五年前ぐらいだろうか。当時出版社から頼まれていた本を担当していた女性の編集者からもらった手帳の切れ端で、小さな手帳から引きちぎられた跡がはっきりとわかる。そこには、茨木のり子の「自分の感受性ぐらい」と題するこの詩の全編が手書きの小さな、きちょうめんな字で1ページにおさまるように書いてあった。
手帳の切れ端を何度も読み返しながら、その人がこの詩を手帳に綴じていた気持ちがわかるような気がしたが、それをちぎってなぜ僕にくれたのか、そのいきさつは、思い出そうとしても思い出せない。
しかし、今になって分かったことがある。僕は、自分の感受性を、自分で守るために、公認会計士になったのだと。誰もが、それぞれの場処で、それぞれのやり方で、そうしてきたように。